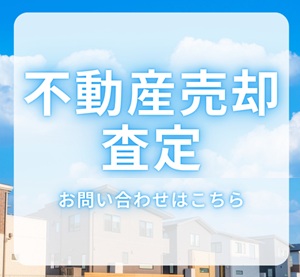ポストに「不動産を売りたい方いませんか?」「近隣で売主を探しています」などのチラシが入っていて、気になったことはありませんか?
最近では、不動産売却を促すチラシが新聞折込やポスティングで頻繁に配布されています。中には大手不動産会社が出しているものもあれば、地域密着型の中小業者が発行している場合もあります。
しかし、どんな会社のチラシでも「電話して大丈夫なのか」「営業がしつこくないか」と不安になる方も多いでしょう。
この記事では、不動産売却チラシの種類や目的、電話した場合の流れ、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説します。読後には、「どのチラシが信頼できて、どんな場合に連絡すべきか」が明確になります。
不動産売却のチラシ事例と概要
不動産売却を促すチラシには、いくつかのタイプがあります。新聞折込やポスティングなど配布方法は同じでも、内容や目的は大きく異なります。まずは代表的なチラシの種類を見ていきましょう。
どんな種類のチラシがある?
不動産売却のチラシには、主に次の3タイプがあります。
- ① 新聞折込に入っている「エリア相場紹介型」
- ② 特定の物件を狙って配布される「ピンポイント型」
- ③ エリア全域に配布する「無作為ポスティング型」
一見どれも似た内容に見えますが、実は「どの会社が出しているか」「どんな目的で配っているか」で信頼性が大きく異なります。
なぜ自宅ポストに入るのか?(配布ターゲティングの仕組み)
不動産会社は、「過去に売買が多かった地域」や「古い住宅地」を狙ってチラシを配布します。
新聞折込やポスティング業者を利用している場合も多く、個人情報を使っているわけではありません。あくまでエリア単位での広告活動です。
またそれらとは別で、本当に特定の家にピンポイントで入れる場合もあります。これは以降の章で解説します。
チラシの目的は「査定依頼を取ること」
これらのチラシの最終的な目的は、「あなたの不動産を売ってほしい」ではなく、まずは査定依頼をしてもらうことにあります。
不動産会社にとって、売却の委任契約(媒介契約)を結ぶことが最初のステップです。そのため、「近隣で売却希望者を探しています」「〇〇町で購入希望のお客様がいます」といったキャッチコピーで関心を引くのです。
新聞折り込みに入ってる不動産売却のチラシ
新聞に折り込まれて配布される不動産チラシは、比較的信頼性が高いケースが多いです。全国展開している大手不動産会社や、フランチャイズに加盟している地域の中堅業者が発行している場合がほとんどです。
新聞折込チラシは広域エリアをカバー
新聞折込チラシは、市区町村や鉄道沿線ごとなど、広いエリア単位で配布されるのが特徴です。新聞販売店の配達エリアを活用できるため、「〇〇市全域」や「〇〇線沿線」など、広範囲に情報を届けます。
多くは「売却物件募集中」「無料査定実施中」といった訴求内容で、地域の地価相場や過去の売却実績を紹介する形式が一般的です。
大手不動産会社・FC系が中心
新聞折込チラシを出すには、印刷費・折込費用など広告コストがかかります。数万部単位で配る場合、1回あたりの費用は数十万円にもなるため、大手や資本力のある会社が中心になります。
こうした会社は、自社ブランドや安心感を前面に出し、「実績」「取引件数」「エリアNo.1」などのキャッチコピーで信頼を訴求する傾向があります。
地域相場や実績を掲載して信頼性を訴求している
新聞折込チラシには、「〇〇町の土地、坪単価〇万円」「最近の成約事例紹介」といった具体的な情報が掲載されていることが多いです。これは、地元で活動していることを示す“信頼の証”でもあります。
ただし、掲載されている成約事例や価格は「平均値」であり、すべての物件が同じように売れるわけではありません。あくまで目安として参考にするのがよいでしょう。
特定の物件を狙って入る不動産売却のチラシ
ポストに「〇〇町の○丁目周辺で、購入希望のお客様がいます」と書かれたチラシが入っていたことはありませんか? このタイプは、特定エリアや物件を狙って配布される“ピンポイント型”の不動産チラシです。
「このエリアで買いたいお客様がいます」は本当?
この文言は、実際にそのエリアで購入希望者がいるケースはまずありません。その購入希望者のためにわざわざ費用かけて広告しないからです。
多くは査定依頼を促すための営業コピーです。 「今すぐ売りたい」「近所に知られずに売却したい」と考える所有者の関心を引く効果があるため、頻繁に使われます。
相続登記を調べている/空き家かどうか調べている会社がある
相続があったときは不動産の所有権が相続人に移転します。その登記簿を法務局から有料で取得(誰でも取得できる)している業者があります。
不動産の登記簿には「相続したかどうか」「所有者住所・氏名」が記載されていますから、そこの住所宛にチラシを直接入れることも可能になるのです。
相続したということは、その不動産が空き家の可能性があるので、とりあえずチラシを入れてみる・・という流れになるわけですね。
あとは人海戦術で空き家かどうかを調べている会社もありますので、そこから情報を仕入れて社員が直接ポスティングしてチラシを入れることもあります。
査定や訪問依頼につなげる営業戦略のひとつ
不動産売却チラシの最終目的は、売主から査定依頼をもらうことです。つまり、「お客様がいます」という表現も、“まずは話を聞いてみたい”と思わせるマーケティング手法のひとつです。
個人的にはそういう広告表現はいかがなものかなと思いますが。
不動産「売却」のチラシ表現は規制されていないため多くの不動産会社は、地域の販売動向をもとに「このエリアならニーズがある」と判断して、すこしフックになうような表現で配布しています。
無作為にばらまかれる不動産売却のチラシ
ポストに「近隣で不動産を探しています」「無料査定受付中!」といったチラシが頻繁に入ることがあります。これがいわゆる無作為配布型のチラシです。
エリアを絞らず大量に配布される
このタイプは、特定の住所や物件を狙うものではなく、町全体・学区全体などを対象に一括ポスティングされるケースが多いです。 配布単価が安く、1万~3万枚単位でばらまけるため、小規模な不動産会社でも実施しやすい方法です。
内容は「無料査定」「買取強化中」「売却物件募集中」など、どの地域にも当てはまるような一般的なコピーが多く見られます。
小規模・地元密着の会社が多い
このような無作為配布型チラシを出すのは、地元密着型の不動産会社であることが多いです。 地域の地価相場や取引履歴に詳しく、実際にその地域で売却活動を行っているケースも多いのが特徴です。
広告費が限られるため、新聞折込よりもポスティングに重点を置き、スタッフが自ら配っている会社も少なくありません。こうした業者は、地域住民との接点を増やす目的でチラシを活用しています。
すぐ電話せず、会社の情報を確認するのが安心
ただし、すべての業者が誠実とは限りません。なかには「査定だけして契約を迫る」「後から他の営業をかけてくる」などのトラブル事例も報告されています。
チラシが気になったら電話をしてみる?

大丈夫な会社かどうかの判断基準としては、会社名や宅建業免許番号、所在地などが明確に記載されているかどうかを確認しましょう。
スマホをお持ちならネット検索してその会社を調べてみてください。またGoogleマップでその会社を見つけてみてください。実在するか、利用者の評価はどうか判断材料になります。
ホームページを見て会社の沿革やスタッフ紹介がきちんと掲載されていれば、信頼度は高いといえます。
これもご縁だと思う方もいますし。地元に根ざした会社であれば、過去の売却事例を見せてもらうなど、具体的な実績をもとに相談するのがおすすめです。
チラシの連絡先に電話するとどうなるか?
「不動産を売りたいけど、チラシの会社に電話しても大丈夫なのかな?」と不安に思う方も多いでしょう。 ここでは、実際にチラシに書かれた番号に連絡した場合に、どんな流れになるのかを解説します。
① 最初の電話対応:担当者が査定の目的をヒアリング
まずは担当者が電話に出て、「どの物件をお持ちですか?」「売却のご予定時期は?」などの簡単なヒアリングがあります。 この段階で「査定だけしてほしい」など希望を伝えておくと、しつこい営業を避けやすくなります。
② 訪問査定を提案されることが多い
多くの会社は、実際に現地を見ないと正確な査定額を出せないため、訪問査定を提案してきます。 このとき、希望がなければ「現地はまだ見せられない」「机上査定だけで」と断っても問題ありません。
もし訪問査定を依頼する場合は、会社のホームページで実在を確認し、担当者の所属や氏名を聞いておくと安心です。
③ 査定後の営業連絡が続くことも
査定を受けたあと、不動産会社から「その後のご予定どうですか?」と営業連絡が入るケースがあります。 これがストレスに感じる場合は、「今回は依頼しません」「今は検討していません」と明確に伝えれば問題ありません。
多くの会社はコンプライアンスを重視しており、きちんと断ればそれ以上の営業を控えるようになっています。
④ 連絡前に確認すべき3つのポイント
- チラシの会社名・住所・免許番号が明記されているか
- 担当者のフルネームを名乗っているか
- 公式サイトやGoogleマップで所在地が確認できるか
これらを確認しておけば、万が一トラブルになっても安心です。 逆に、住所が書かれていない・個人携帯番号のみなどのチラシは避けましょう。
大手か地元の有力不動産会社ならまだ安心
不動産売却のチラシには、全国展開の大手企業から、地域密着の小さな不動産会社まで、さまざまな業者が存在します。 どの会社に連絡するかによって、売却の進め方や対応のスピード、得られる情報量が大きく異なります。
大手不動産会社の特徴
大手不動産会社は、広い販売ネットワークと高い知名度が強みです。 全国的な広告展開や自社サイトの集客力があり、都市部の買主にもアプローチできるため、物件の露出度が高くなります。
一方で、地域特有の事情(市街化調整区域、農地、古家付き土地など)には詳しくないケースもあり、 担当者によっては現場判断にばらつきが出ることもあります。
- メリット:販売力・広告力が高く、安心感がある
- デメリット:地域の細かな事情には疎い場合もある
地元密着型の不動産会社の特徴
地元密着型の会社は、その地域の地価・土地の履歴・地元買主の動きに精通しているのが強みです。 現地の不動産を数多く扱っており、実際にそのエリアでどんな物件がどの価格で売れたか、リアルな情報を持っています。
特に野田市のように、市街化調整区域・農地・古家付き土地などの特殊な不動産が多い地域では、 全国チェーンよりも地元の専門会社のほうが正確な査定・提案ができるケースも多いです。
- メリット:地域事情に詳しく、対応が柔軟
- デメリット:広告力・知名度は大手に比べて劣る場合も
どちらを選ぶかは目的次第
「とにかく高く売りたい」「広く買主を募りたい」なら大手、 「地域事情を踏まえて確実に売りたい」「農地や調整区域の売却相談をしたい」なら地元の有力不動産会社がおすすめです。
理想は、複数の会社で査定を受けて比較し、それぞれの提案内容や担当者の対応で判断すること。 最終的には「信頼して任せられる担当者かどうか」が決め手になるでしょう。
「買取ります」と書いてあったのに連絡がない…そんなときは
不動産のチラシを見て連絡し、査定まで進んだのに、その後ぱったり連絡が途絶える――そんな経験をされた方もいるかもしれません。
このような場合、ほとんどは「不動産会社側で買取が難しいと判断された」ケースです。 採算が合わない、再販しても利益が出ない、法的な制限(市街化調整区域・再建築不可など)があるといった理由で、“買取対象外”と判断された可能性があります。
チラシに「買取ります」と書いてあっても、実際はすべての物件を無条件に買取できるわけではありません。 ほとんどの不動産会社は「再販売できるか」「リフォーム後に需要があるか」などをシビアに見極めた上で、採算が取れる場合のみ買取を行います。
ただし、連絡がないまま放置されるのは気分が悪いものです。 1週間ほど待っても返答がない場合は、「今回は買取の見送りでしょうか?」と確認してみましょう。 それでも対応がない場合は、別の会社に査定を依頼した方が早く進む可能性があります。
有限会社ミューファは、野田市を拠点に不動産事業を行っております。
地元に根ざした活動を大切にしており、おかげさまで多くのお客様からご紹介を通じてご依頼をいただいております。
まだチラシなどでのご挨拶はできておりませんが、弊社の不動産売却サポートにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひこちらをご覧ください。
野田市で不動産売却なら