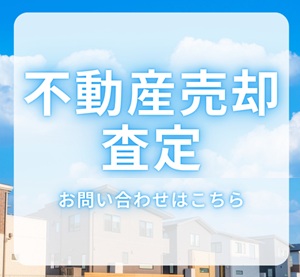「農地を売りたいけれど、どうすればいいのかわからない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
相続で畑や田んぼを受け継いだものの、使う予定がなく管理が負担になっている方や、農業を引退して農地を手放したい方は少なくありません。ところが、農地は宅地やマンションのようにすぐには売れないのが実情です。
不動産屋に相談しても、「ウチでは買い手を探すには難しい」と断られる案件でもあります。
なぜなら、農地を売るには農地法に基づく許可や手続きが必要だからです。これを知らずに進めると、「買い手が見つからない」「そもそも売却できない」といった悪循環に繋がりかねません。
この記事は、野田市で不動産屋、司法書士、行政書士を営む(有)ミューファが、これまで農地を扱ってきた経験から
- 農地を売るために必要な手続きや許可
- 畑、田んぼを売るときの注意点
- 売れない農地を売却できる可能性
をわかりやすく解説します。
「農地を売るにはどうしたらいいの?」と迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
農地を売るにはどうすればいい?
農地が自由に売れない理由(農地法の規制)
農地が売りにくい理由は「農地法」にあります。
農地法では、農地を守り食料生産を確保するために、農地の売買や転用に厳しい制限を設けています。もし規制がなければ、農地がどんどん宅地や駐車場になり、農業が成り立たなくなる恐れがあるからです。
つまり、農地を売るときは「誰に売るのか」「その土地をどう使うのか」に応じて、必ず法律に基づいた許可が必要になります。
農地を売る方法
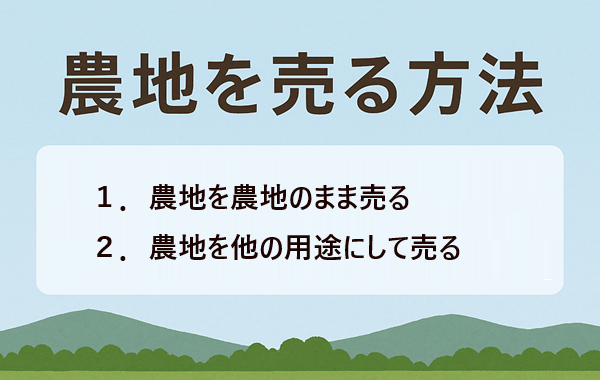
農地を売るとき、多くの場合で市区町村の農業委員会による許可が必要です。代表的なケースは次の2パターンで売却することができます。
①農地を農地のまま売る場合
→「農地法第3条」に基づく許可が必要
(農業を続ける人に売るための手続き)
②農地を売って宅地や駐車場にする場合
→「農地法第5条」に基づく許可が必要
(農地を農地以外の用途にする=農地転用)
許可なしで売買契約を結んでも、その契約は無効となってしまいます。つまり「買い手が見つかった=すぐに売れる」わけではなく、まずは次のような農業委員会の許可を得ることが大前提です。
| 内容 | 許可 | 市街化区域なら |
|---|---|---|
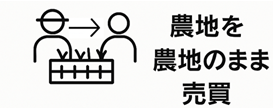 | 農業委員会許可 | |
 | 農業委員会/県知事許可 | 届出でOK |
この表をご覧いただくと、農地が「市街化区域」にあるかどうかでかなり変わってきます。市街化区域にあり都市計画法に適合する用途であれば「届出」で売買が可能になります。
そうすると、市街化調整区域にある農地のほうが売買が困難になってくる、という訳ですね。
農地売却の基本的なステップ
農地を売るときの大まかな流れは次のとおりです。
①農地売却に精通している不動産屋に買主を探してもらう
②売買契約の締結
③農地法の許可申請を行う(売主・買主共同で)
売買契約書では許可が出ることを条件として契約が有効になるようにしておく。
④許可が下りる
⑤決済&引き渡し、所有権移転登記を行う
司法書士に法務局で登記手続きを行ってもらい、正式に買主へ名義が移ります。
農地を売りたいときに必要な手続き
農地法第3条の許可(農家へ売る場合)
農地を農業を続ける人に売る場合は、農地法第3条の許可が必要です。これは「農業を営む意思と能力のある人にしか農地を譲渡できない」というルールです。
具体的には、次の条件を満たす必要があります。
- 買主が原則農業従事者または農業法人であること
- 経営面積が一定以上になること(都道府県ごとに基準あり)
- 実際に農地を耕作できる体制を持っていること
この許可を得ることで、「農地を農地として使い続ける」という前提で売買が成立します。
しかし現実には、買いたいという農家が少ない(見つからない)ので、農地が売れない、売れにくいという状況が多いのです。
農地法第5条の許可(買って宅地などへ転用する場合)
農地を宅地や駐車場など、農地以外の用途に変えて売る場合は、農地法第5条の許可が必要です。これは「農地転用」と呼ばれる手続きで、宅地造成や建物建築の前提となります。
例えばこんなケースが該当します。
- 農地を住宅用地にして家を建てたい
- 農地を駐車場、資材置き場、太陽光発電に変えて活用したい
宅地で売るほうが買い手が付きやすいので、宅地に出来る土地のほうが価値も高くなる傾向にあります。
農地転用には立地条件や地域の都市計画の制限も関わるため、許可が下りないケースもあります。特に市街化調整区域にある農地は厳しく制限されるので注意が必要です。
届出または許可申請方法と必要書類
野田市では市街化区域と市街化調整区域にある農地転用で以下のように届出/許可が異なります。
| 農地転用の届出について (市街化区域内の場合) | 農地転用の許可について (市街化調整区域内の場合) | |
|---|---|---|
| 許可 | - | 農業委員会→都道府県知事 |
| 届出 | 農業委員会 | - |
| 事前相談 | 農地法第4・5条転用許可の可能性を相談 | |
| 必要書類 | 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出 | 農地法第4・5条の規定による許可申請 |
申請に必要となる主な書類は以下の通りですが、詳細は野田市のHPをご確認ください。
- 農地転用届出書
- 案内図、公図
- 売買契約書
- 土地の登記事項証明書
- 転用計画に関する資料
- 買主の農業経営に関する書類(第3条許可の場合)
審査にはおおむね1〜2か月ほどかかり、許可が下りて初めて有効な売買契約になることができます。
野田市の許可申請受付期間
野田市の場合、農地法の許可申請は毎月20日~24日(土日除く開庁時間内)と決まっています。(年度により違う場合あり)
毎月月末に受付となり、翌々月の上旬ごろには許可が出る流れです。
市街化調整区域では開発許可も必要
市街化調整区域の農地を買って転用する場合、農地法5条の許可の他に、開発許可が必要になります。
農地は売れないって本当?【売却できないケースと対策】
非農地証明で地目を変更すれば売れるようになる可能性
「土地の地目は畑なんだけど、その上に昔から建物がたってる、資材置き場になっている…」といった、登記簿の地目と現況が異なり一定年数経過している場合に「非農地証明」を受けることで、地目を変えることが可能です。
この場合、農地法の許可を経なくてもこの土地の取引が出来るようになる可能性があります。(ただし非農地証明の可否や条件は自治体により異なる)
弊社ではこの非農地証明の代行から売却までワンストップで行ってきた事例がございます。
市街化調整区域にある農地の場合
農地の中でも特に「市街化調整区域」にある土地は、売却が難しいです。
市街化調整区域とは「原則として住宅や商業施設を建てられない地域」で、都市計画によって制限されているからです。
農地のなかで、1種農地、2種農地のうち「2種農地」は住宅地に近いエリアであったり、農業利用としての重要度が低いため、比較的転用が認められやすいことがあります。
ご依頼いただければ役所にて調査することが可能です。転用許可が出れば売れやすくなると思います。
相続したまま放置されている農地の場合
相続で農地を受け継いだものの、遠方にあったり使い道がなくて放置されているケースも多いです。この場合も、いきなり売ることはできません。前述の農地法の許可は必要ですが、それ以前に相続登記が必要です。
📍名義変更(相続登記)が終わっていないと売却できない
📍草刈りや管理をしていないと買主がつきにくい
対策としては、まず相続登記を済ませ、農地の現況を整理することが大切です。近年は相続登記の義務化も始まっており、放置しておくと罰則のリスクもあるため注意が必要です。
売れない農地を弊社が買い取る方法
弊社では農地買取のご相談をいただくケースも多くございます。
農地の立地条件や将来的な土地活用の可能性によっては、弊社が直接買取を行う場合もございます。
畑・田んぼを売るには?
畑は比較的地盤が安定しており、宅地や駐車場などへの転用もしやすい傾向があります。田んぼを売却する場合は、畑以上にハードルが高くなることがあります。
📍地盤の弱さに注意
田んぼは水を張る前提で造成されているため、宅地にするには大規模な地盤改良が必要な場合があります。盛土や砂利を敷いて駐車場にする手もありますが、やはり費用がかさみやすい点に注意が必要です。
📍排水対策が必要
住宅用地に転用する場合、暗渠排水や盛土工事を行う必要があり、コストが増えやすいです。田んぼを売る場合は、造成費用が価格に反映されるので、その分安くなります。
農家住宅は売れない?
私たち不動産屋では、市街化調整区域で建っている建物がどのような許可で建てられたかを役所で調べます。
その際に「農家住宅」として建てられたことが判明する場合があります。
農家住宅は、その多くが「農家である人」しか住めない前提で建てられています。 そのため、購入できる人が非常に限定されており、市場に出しても買い手がつきにくいのが実情です。
また、原則として農家以外の人が賃貸で住むことはできず、建て替えにも制限があります。 こうした条件から、一般市場での流通は難しく、結果として資産価値が大きく下がってしまうケースが多いのです。
違反を承知で買って住むことも不可能ではありませんが、おすすめはしておりません。
農家住宅は賃貸不動産経営の投資家(大家)さんが購入するケースはあります。金融機関の融資対象外であることが多く、現金購入が基本となるでしょう。そのため売買価格は現金で買える範囲に絞られます。
農地の売却査定額はいくら?
農地の査定方法と相場の目安
農地の査定額は、宅地やマンションのように一律の相場表があるわけではなく、個別の条件によって大きく変動します。
一般的には以下のような価格帯になります。
①農地のまま売る場合
→ 1㎡あたり数百円〜数千円程度が多く、立地によっては宅地の数分の一以下になることもあります。
②宅地転用できる農地の場合
→ 住宅用地や事業用地としての需要が見込めるため、査定額は農地のままより高くなります。
「農地の売却査定額はいくら?」という疑問には、単純な数字だけで答えることはできません。 しかし、立地・接道・転用可能性といった条件を把握することで、おおよその価値を見極められるようになります。
一度弊社の不動産売却査定よりお問合せください。
相続した土地・建物と農地を売却したい場合のポイント
親から相続した実家(土地と建物)と、周辺にある農地を処分したいと考える方もいらっしゃいます。
売却できる資産を整理する
親から相続した資産が「自宅の土地・建物」と「農地」に分かれている場合、それぞれで売却条件が異なります。
📍土地・建物(宅地)→不動産会社を通じて一般的に売却可能
📍農地→農地法の許可が必要で、自由には売却できない
どの土地がウチの土地なのかわからない、という場合は、名寄帳を取得して、所有するすべての土地を把握します。
固定資産税の通知書や登記簿などで、どの土地が宅地でどれが農地なのかを確認しましょう。
まとめて売る?別々に売る?
処分したい場合はまとめて売りたいところですが、残念ながら農地は自由には売却できません。この場合も宅地と一緒に売りたいなら、農地転用するか非農地証明か、業者に一括で買い取ってもらうのがスムーズです。
野田市で行う、農地から開発・建築の流れ
農地を宅地に転用して、建築をしていく流れは以下のように開発許可をセットなっております。ですので土地を買ってすぐに家を建てられるわけではありません。
↓
造成計画図の作成
都計法開発29条申請、農転5条申請
↓
開発許可&農転許可
↓
都計法37条申請・建築確認申請(確認済証)
↓
建築工事
↓
都計法29条・農転5条完了検査
↓ ↓
↓ 建築確認検査
↓ ↓
検査済証 検査済証
一般人が農地を農地として買うには?
農地を購入できる人の条件
農地は、誰でも自由に買えるわけではありません。 購入できるのは「農業を適切に行える人」に限られ、農地法第3条に基づく許可を受ける必要があります。
具体的な条件は以下の通りです。
- 自分または家族が農作業に常時従事できること
- 一定の経営面積を確保できること(都道府県ごとに基準あり)
- 継続的に農業を営む意思と能力があること
- 新規営農希望者
つまり「趣味で少し畑をやりたい」といった目的では原則として購入できず、農業に取り組む人が対象となります。(一般的には年間150日以上目安)
個人やサラリーマンでも買えるケース
「サラリーマンでも農地を買えるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
結論としては、条件を満たせば可能ですが、例えば、次のようなケースがあります。
- 定年後に本格的に農業を始める予定があり、必要な面積を確保する場合
- 農家資格を取得し、農業を継続する意思を示す場合
- 農業法人を設立し、法人名義で購入する場合
ただし、一般の会社員が「家庭菜園用に農地を買いたい」というだけでは許可が下りないかもしれません。その場合は「市民農園の利用」や「貸し農園」を活用するのが現実的な方法だと思います。
どうしても売れない農地、最終的にはどうすればよい?
立地や売れる条件を調べた結果、どうしても売れない、ということが起こります。そのような時は農地バンクの活用/相続土地国庫帰属制度をご案内いたします。
1. 農地中間管理機構(農地バンク)に貸す
国が整備している「農地中間管理機構(農地バンク)」を通じて、農地を貸し出す方法があります。
- 農業を続けたい人に貸し付けられる
- 自分で管理する手間が減る
- 売却ではなく賃貸なので所有権は残る
👉 「売れないけれど手放したい」「管理の負担を減らしたい」という方に有効です。
2. 相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年から始まった制度で、条件を満たせば相続した不要な土地を国に引き渡せます。
・農地の場合は「耕作放棄地」など管理が困難な土地も対象
・審査(14000円)と負担金(原則20万円)が必要
・行政書士等に申請代行する費用(約30万円)
・承認されれば、以後の管理責任や固定資産税の負担がなくなる
👉 「どうしても売れない・活用できない」という場合の最終手段として注目されています。
農地の処分を考えたらミューファにご相談を
不動産の売却・処分・査定のご相談はこちらからお願いいたします。
お客様の農地の売却について一緒に考えさせていただきます。