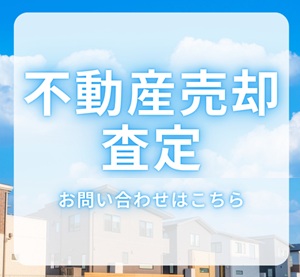不動産を売却しようと考えたときに、多くの方が気になるのが「具体的な流れはどうなっているのか」という点です。
不動産の売買に関する情報はあふれていますが、具体的な動き方が書かれていない場合がほとんどなので、記事にしました。
不動産売却といっても、
・通常の仲介で売却するケース
・不動産会社に直接「買取」してもらうケース
・住宅ローン返済中の売却
・相続や離婚、成年後見人が関わる売却
など、状況によって流れや必要な手続きが変わってきます。
この記事では、不動産売却の基本的な流れから、期間の目安、契約・決済のプロセス、そして相続・離婚・後見人が関わるケースまでをわかりやすく解説します。
初めての方でも全体像がつかめる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却の基本的な流れ

不動産屋に相談~査定の申し込み(机上査定と訪問査定)
不動産売却の第一歩は「いくらで売れるか」を知ることです。
査定には大きく2種類あります。
①机上査定:所在地や面積、築年数などの基本情報をもとに、おおよその相場を算出する方法。短時間で結果がわかります。
②訪問査定:実際に不動産会社の担当者が現地を確認し、建物の状態や周辺環境、過去の成約事例をもとに査定額を算出する方法。より正確な価格がわかります。
将来的に売却することが決定している方は、正確な売却価格を知るために最初から訪問査定をご依頼いただくケースが多い印象です。
価格提案と売却活動の開始
査定を依頼した不動産会社から提示された価格を参考に、売主自身が「売り出し価格」を決定します。このとき、「早く売りたいのか」「できるだけ高く売りたいのか」によって価格設定が変わります。
不動産会社に本格的な販売活動を依頼します。これを「媒介契約」といいます。媒介契約を締結したら不動産屋も本格的に作業を開始し、売り出し価格が決まったら、販売活動が始まります。
・チラシや看板での広告(昨今紙のチラシはほとんど使われません)
・不動産会社のネットワークを活かした紹介
といった方法で買主を探していきます。
購入や内覧希望者から問い合わせ(メールやTEL)が不動産屋に来ますので、彼らの対応を行います。一緒に現地の家に行って内覧してもらったり質問対応を行います。
買主が購入する意欲があれば、購入申込書に記入していただき、売主さんにお伝えします。
売買契約から決済・引渡しまで
売主と買主の間に入って条件交渉を行い、合意に至れば次へ進む流れです。
不動産屋から買主に対して「重要事項説明」を行います。これは不動産屋の義務で、売買対象の不動産に関する都市計画や建築基準法の規制、不動産そのものの状態、契約条件などを説明するものです。この説明を受けて問題なければ売買契約に進みます。
売買契約は一般的には不動産屋の事務所に、売主・買主が集合して行います。(遠隔地の場合はITを使った手続きも可能)
売買契約書を読み合わせ問題なければ、両者署名・押印をして買主→売主へ手付金が支払われます。
契約~決済までの間は準備期間です。
買主:残代金の準備(ローンの申し込み等)
売主:残置物の撤去、隣地の人と確定測量の合意、不具合の修補、引越し準備等
お互いの準備ができれば、決済へ進みます。決済は不動産屋の事務所か、銀行に集合して行います。(同時に司法書士立会い)
買主→売主へ残代金が支払われ、売主が着金を確認すれば、売主→買主へ鍵を引き渡します。司法書士が法務局に不動産の所有権移転登記をしに行きます。ここまでを1日で行います。
後日、移転登記が完了し、登記識別情報が送られていきます。
これで不動産売却の基本的な流れが完了です。
弊社では司法書士が在籍していますので、決済後の移転登記までスムーズな手続きが可能です
司法書士や金融機関の立会いと、受領書決済、自動決済(送金決済)について
決済時には司法書士が必ず立ち会い、所有権移転登記や抵当権抹消の手続きを確認します。また、住宅ローンを利用する買主がいる場合は、金融機関担当者も同席して融資実行を行います。これにより、売主・買主双方が安心して安全に取引できる仕組みになっています。
売主・買主が遠隔地だったりして銀行に集合できない場合、次の①②の方法で遠隔地からの銀行振り込み等で決済を行います。
①受領書実行の場合
受領書とは登記申請時に法務局窓口で発行してもらえる証明です。
司法書士から銀行に受領書をFAXし、銀行がそれを確認したら融資を実行する流れです。
所有権移転登記→お金の支払いという流れになります。
②自動実行(自動決済/送金決済)の場合
この用語は地方や慣習により異なるかもしれません。
買主が売主に送金し、売主が着金確認後に、司法書士へ連絡し、所有権移転登記を申請する流れです。
不動産売却にかかる期間の目安
査定から売却活動開始まで1~3週間
査定の依頼から結果が出るまでは、机上査定なら即日〜数日、訪問査定でも1週間前後で結果がわかります。
その後、売出価格の決定や広告準備を経て、販売活動のスタートまでは1~2週間程度が一般的です。
売却活動~買主決定まで3~6か月
不動産の種類や立地によって差がありますが、買主が見つかるまでには3〜6か月程度が目安です。
駅近や人気の住宅地では1〜2か月で成約することもありますが、需要が少ない農地や市街化調整区域の物件は1年以上かかるケースもあります。
契約から決済・引渡しまで1~2か月
売買契約が成立してから決済・引渡しに至るまでは、通常1〜2か月程度です。
不動産会社に直接「買取」してもらう場合の流れ
不動産屋の仲介で売る場合とは別で、不動産屋が直接買取る場合の流れもお伝えします。
買取は、不動産会社が買主となり直接購入する方法ですので、流れはシンプルですね。
↓
条件が合えばすぐに売買契約
↓
決済・引渡し
という短期間で完了します。
早ければ1か月かからずにお金が振り込まれるケースもあるでしょう。
仲介売却よりも売却価格は相場の5〜9割程度に下がるのが一般的です。「早く現金化したい」「近所に知られず売りたい」といったケースに向いています。
高額な査定の場合は、買取業者の予算次第では買えない場合ももちろんあります。
住宅ローン返済中の不動産売却の流れ
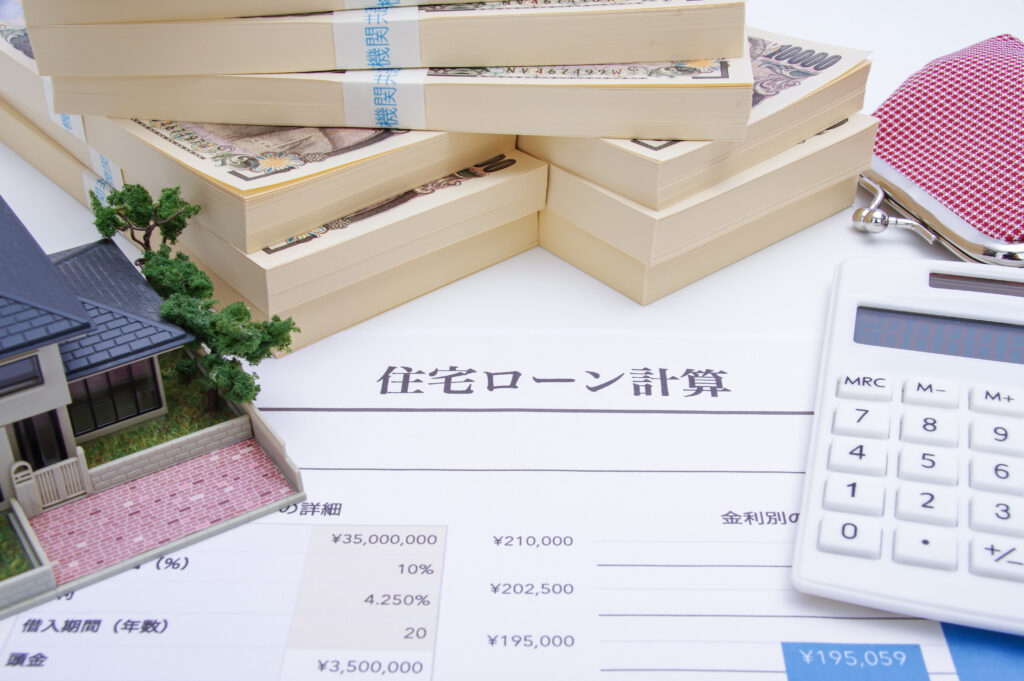
ローン残債の確認と抵当権抹消の手続き
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、まずは残債額の確認が必要です。
売却代金でローンを完済し、同時に金融機関を通じて抵当権の抹消登記を行うのが基本的な流れです。
売却代金でローンを完済する仕組み
決済時に買主から売主へ残代金が支払われ、その一部を金融機関へ返済してローンを完済します。
司法書士が立ち会い、抵当権抹消と買主への所有権移転登記が同日に行われるため、買主・金融機関双方に安心して取引してもらえます。
任意売却の流れ(残債が残る場合)
売却代金でローンを完済できない場合は「任意売却」を検討します。
金融機関の同意を得て、残債を分割返済する条件、あるいは別途現金を用意して売却を進める方法です。
競売に比べて高値で売れる可能性があり、売主にとっても負担が軽減されるケースがあります。
不動産売却後に必要な確定申告の流れ
税の相談は税理士へ、というのが基本ですので、一般的な話になります。🙇
譲渡所得税の計算方法
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年に確定申告を行い、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 譲渡価格(売却額)-(取得費+譲渡費用)
取得費:購入時の価格や購入諸費用(相続物件の場合など、当時の書類を探してください)
譲渡費用:仲介手数料、測量費、解体費など売却に直接かかった費用
計算結果がプラスであれば課税対象、マイナスなら申告不要です。
3,000万円特別控除や特例の利用
居住用財産を売却した場合、譲渡益から最大3,000万円まで控除できる「特別控除」が利用可能です。こうした特例を活用することで、税負担を大きく減らすことができます。
確定申告の流れ
流れというほどでもありませんが、確定申告は売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に行います。eTAXを使ってネットで申告もできますがPCに慣れてない人が操作するのは結構大変だと思います。
税額計算や控除の判断が難しい場合は、税理士に相談するのも安心です。
状況別にみる不動産売却の流れ
相続した不動産を売却する場合

相続した不動産を売却する場合、まずは相続登記を行い、所有者名義を被相続人から相続人へ移す必要があります。名義変更が済んでいないと売却契約はできません。
遺言がない場合・遺産分割協議が未成立時の不動産売却の流れ
1. 相続人の確定
まず誰が相続人かを確定します。被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を出生から死亡まで集め、法定相続人を確認。相続人調査は司法書士や弁護士に依頼することも多いです。
2. 相続登記(名義変更)の前に、遺産分割協議が必要
相続人が複数人いる場合、遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行います。(決まらなければ裁判所で調停申立)
この協議で「不動産を誰の名義にするか」「売却して代金をどう分けるか」を決めます。全員一致が原則です。1人でも同意しなければ売却はできません。
相続人が複数いる場合の分け方の話
換価分割でわける
相続人全員で不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分ける方法です。
または1人が取得して売却して現金化し、そのお金を相続人で分ける方法もあります。
代償分割でわける
不動産を特定の相続人が単独で取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法です。
→たとえば、長男が実家に住み続けたい場合、実家を長男が相続し、他の兄弟には代償金(見合いのお金)を支払います。
3. 遺産分割協議書の作成
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印押印。
4. 相続登記(所有権移転登記)
遺産分割協議書に基づいて、司法書士に依頼し相続登記を行います。この登記をしないと、そもそも売買契約を結べません。
5. 不動産屋への売却活動の依頼
あとの流れは基本的な売却の流れと一緒です。不動産が共有名義の場合は名義人全員の署名・押印が必要になります。
離婚に伴う不動産売却の流れ

事前に話し合うべきこと(名義・ローン・分配ルール)
離婚に伴う不動産売却では、まず夫婦間でルールを決めることが重要です。
- 名義の確認
単独名義か共有名義かで手続きが異なります。共有名義の場合は、相手の同意なしに売却できません。 - 住宅ローンの残債
ローンが残っている場合、売却代金で完済できるのか、完済できないなら任意売却にするのかを話し合う必要があります。 - 売却代金の分配方法
共有持分割合に応じて分ける、財産分与の一環として折半、慰謝料や養育費に充てるのかなど、合意しておくことがトラブル回避につながります。
不動産売却の流れ
離婚に伴う不動産売却は「離婚前に売却して清算する」方法と「離婚後に売却する」方法の2つがあります。
住宅ローンの有無や名義の状況によって最適なタイミングが変わるため、どちらが良いか迷うときは専門家に相談するのが安心です。
不動産売却自体の流れは、基本の流れと一緒で、「査定→販売活動→契約→決済・所有権移転」とたどります。
不動産屋の訪問査定のときに
離婚に伴う売却では、周囲に事情を知られたくないというご要望をいただくことがあります。
そのため「訪問査定はできるだけ短時間で」「目立たないよう私服で来てほしい」「女性スタッフに対応してほしい」「周りに人が居ない夜間に」といったリクエストをいただくケースも少なくありません。
もちろん可能な限り配慮いたしますが、不動産会社の体制上、必ずしもすべてのご要望に対応できない場合もあるのが実情です。
「プライバシーを守る」「ご近所に知られにくい形で査定・売却活動を進める」ことを重視し、最大限の対応します。
成年後見人による不動産売却の流れ
所有者本人が認知症などで判断能力を欠いている場合、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て売却手続きを進めます。
通常の売却に比べて手続きが煩雑で、売却までに時間がかかることが多いのが特徴です。
後見人が関与する場合は、裁判所への申立書類や証明書の準備なども必要になるため、司法書士や弁護士といった専門家のサポートが不可欠です。
まとめ|不動産売却の流れを正しく理解して安心の取引を
不動産売却は、人生の中でも大きな取引のひとつです。
「査定 → 販売活動 → 契約 → 決済・引渡し」という基本の流れはシンプルに見えても、実際には 住宅ローンの精算、相続や離婚、税金の申告、境界確定や残置物処理 など、さまざまな課題が関わってきます。
流れを正しく理解し、自分の状況に合った売却方法を選ぶことができれば、トラブルを避けて安心して取引を進められます。
大切なのは、高く売りたいのか、早く売りたいのか 自分の優先順位を明確にすることだと思います。
また、事前に以下のような準備をしておくとスムーズに進められます。
・購入時の資料(間取図、建築確認、設計図、パンフレット、重要事項説明書、契約書等)
・固定資産税の通知書
・アピールポイント、既存の不具合箇所、近隣との申し合わせ事項等
弊社にご興味がおありでしたら、ミューファの不動産売却をご覧ください。